京都烏丸六角アートプロジェクト

- 主催
- 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
- 協賛
- 株式会社京都建築事務所、日本建設株式会社、株式会社ビルネット、株式会社三菱UFJ銀行、宗教法人六角仏教会 協 力 中央フードサービス株式会社
受賞作品

最優秀賞
蘭花指II-12023年 606×727

周 逸喬
- PROFILE
- 京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻 1回生
- COMMENT
- この度は博士課程を修了する際に、最優秀賞を頂きまして誠にありがとうございます。インテリアには絵画作品を装飾するのが普通ですが、その中に私の漆平面作品を選んで頂きとても光栄を感じます。今後はアーティストビザを取得して日本と中国に作家活動を行っていきつつ、より一層精進していきたいです。

優秀賞
夢巡る2023年 1,167×910

渡邊 京子
- PROFILE
- 京都市立芸術大学 大学院 美術研究科日本画専攻 修士2回生
1999 山梨県生まれ
2021 京都花鳥賞作品展 日本画部門 入賞(京都花鳥館新館)
2022 京都市立芸術大学 作品展 市長賞(京都市京セラ美術館)
2022 同作品展にて作品買い上げ(京都市立芸術大学芸術資料館)
2022 京都春季創画展 入選(京都文化博物館)
2023 個展『繁茂 -Youth to Use ! 2022-』開催(Art Spot Korin)
2022 京都市立芸術大学 作品展 市長賞
- COMMENT
- この度は優秀賞に選んでいただき誠にありがとうございます。この賞をいただけたことを光栄に思います。「夢巡る」は郷愁と樹木の生命力を描いた作品です。この作品から、少しでも自然の持つ力を感じ取っていただけましたらこれ以上嬉しいことはないです。私も今後も樹木から力を分け与えてもらい、精進いたします。本当にありがとうございました。

審査員特別賞
そらまめ2022年 960×960
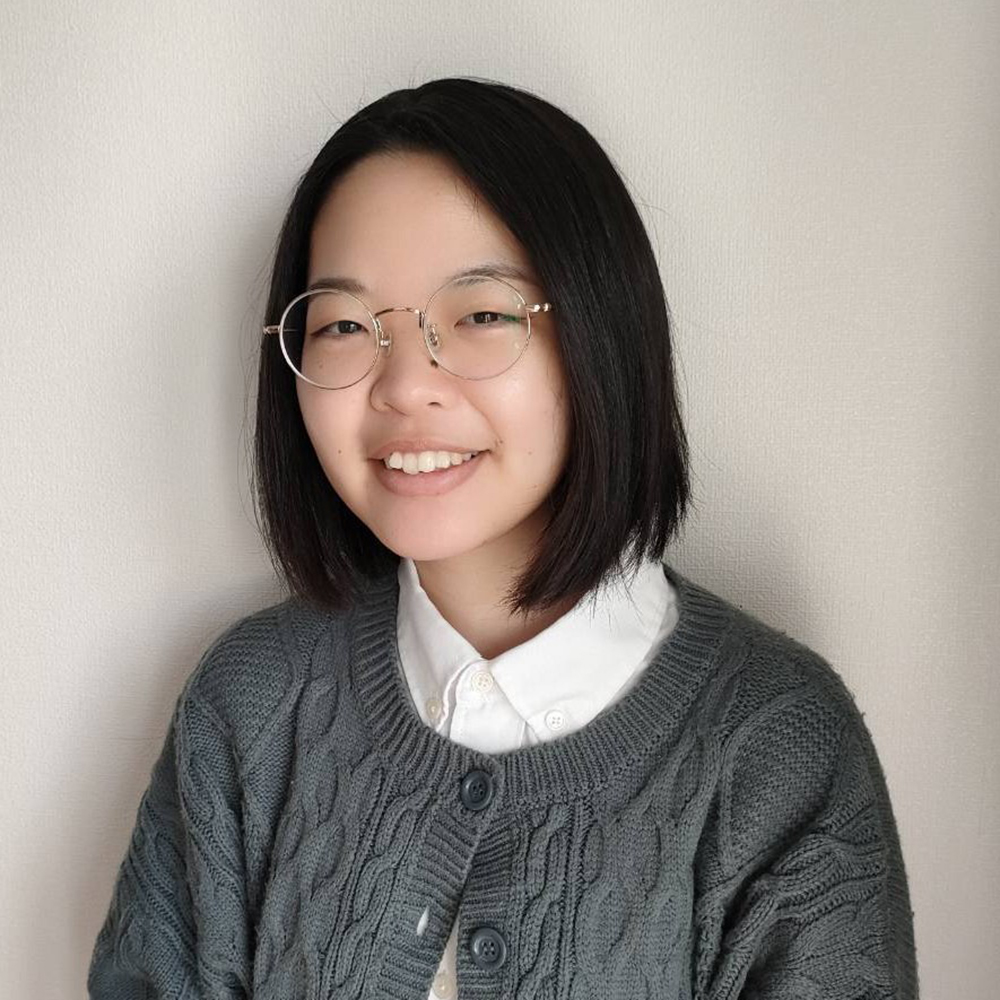
髙橋 由莉
- PROFILE
- 2018年 京都市立芸術大学 入学
2020年 グループ展「ふわふわ展」 ギャラリー35
2022年 2021年度京都市立芸術大学制作展 奨励賞
2022年 京都市立芸術大学 卒業
2022年 京都市立芸術大学大学院 入学
2022年 第9回 京都5美術大学交流展
2023年 2022年度京都市立芸術大学制作展
2023年 3人展「モユル絵展」 綾小路ギャラリー武 - COMMENT
- この度は審査員特別賞を頂き大変光栄に思います。日常の中に作品を飾ってもらえることは大変嬉しく、見る方に喜んでいただけたら幸いです。このような機会をくださりありがとうございます。これからも日々努力することを忘れず精進していきます。

京都建築事務所賞
眠れない夜に2023年 950×1,210

髙田 紗衣
- PROFILE
- 2019年 第56回高槻市美術展覧会 入賞
2021年 グループ展「F6・極2021展」アモーレ銀座ギャラリー
2021年 第5回日春展 入選
グループ展 「京都市立芸術大学日本画専攻 古画研究の現在」 上賀茂神社境内
髙田紗衣×橘葉月二人展「画室のパノラマ」 Norang Narang /ノランナラン/너랑 나랑
第57回高槻市美術展覧会 入選
2022年 グループ展「よりみちアートマルシェ」大垣書店京都本店
第58回高槻市美術展覧会 入賞
2023年 京都市立芸術大学作品展 山口賞
京都市立芸術大学美術科日本画専攻 卒業
- COMMENT
- この度はこのような輝かしい賞をいただき大変光栄に思います。そして私の作品が今後も人の目に触れ続ける機会を与えてくださり、ありがとうございます。作家として冥利に尽きます。眠れない夜にというタイトルの私の作品は、私が夜散歩へ出た際に通りがかった、バラ園を描いたものです。暗闇の中でぼぅっと光る花たちが空から落ちる星々のように見えて、不安で眠れなかった私の心を溶かしてくれるようなそんな情景を表現しました。ご覧になった皆様の心に寄り添う作品になることを願います。ありがとうございます。

三菱UFJ銀行賞
1月3日2023年 803×1,000

佐藤 真優
- PROFILE
- 2022年 京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻 修了
2022年 三人展「またたき」 ANTIQUE belle Gallery(京都)
2022年 「キテミテ中之島」 中之島駅構内(大阪)
2022年 二人展「感覚写真」 京都市立芸術大学小ギャラリー(京都)
2023年 「京都市立芸術大学作品展2022」 京都市京セラ美術館(京都)
2023年 「スクエア ザ ダブル vol.16」 フリュウ・ギャラリー(東京)
2023年 二人展「感覚写真 second exhibition」 kumagusuku SAS(京都)
- COMMENT
- この度は三菱UFJ銀行賞をいただき、大変光栄に存じます。この作品が日々たくさんの方に目にしていただける場所に展示されること、心から嬉しく思います。誰の記憶の奥底にも微かにあるような、多くの人が懐かしさを覚えるような作品を目指して制作いたしました。今後も制作に励んでまいります。

ビルネット賞
青い花瓶2023年 606×727

鈴木 彩衣
- PROFILE
- 京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻 1回生
- COMMENT
- この度はビルネット賞を頂き、誠に光栄です。今後も様々な素材に触れ、常に新しい感性で作品制作に臨めるよう精進して参ります。

日本建設賞
洗面台2021年 1,065×760

柴田 若奈
- PROFILE
- 2023年 京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻 修了
【展示歴】
2019年 進階展(國立台藝術大學/台南)
台湾留学写真展(愛知県立芸術大学/愛知)
木木木(もり)の卒展(愛知県立芸術大学/愛知)
2021年 PORTO DI STAMPA 2021(アートゾーン神楽岡/京都・B-gallery/東京)
2022年 PORTO DI STAMPA 2022(アートゾーン神楽岡/京都・B-gallery/東京)
2023年 個展「昨日あったこと」(Hideharu Hukasaku Gallery Roppongi/東京)
【受賞歴】
2021年 第1回 NAGOYA INNOVATOR'S GARAG 賞 受賞
2021年 第46回全国大学版画展 優秀賞
2022年 第1回 FEI PURO ART AWARD 大賞
第7回星乃珈琲店絵画コンテスト 優秀賞
京都銀行美術研究支援制度選出
京都市立芸術大学制作展 同窓会賞2019年 第56回高槻市美術展覧会 入賞
- COMMENT
- この度は日本建設賞をいただきまして、誠にありがとうございます。本作は私が京都に来て初めて作ったコラグラフ版画であり、その作品を烏丸六角のホームに飾っていただけること、大変光栄に思います。作品がホームの皆様の生活に寄り添えるよう祈念いたします。

六角仏教会賞
hokusai2022年 318×410

林 美紅
- PROFILE
- 京都市立芸術大学 油画 3回生
2021年 BORDER! 2021 ライブペイント
2022年 「Black marketⅡ」SUNABAギャラリー
イロリムラ 個展「言葉にならない言葉について」 produced by SUNABAギャラリー
「ポストカワイイ Ⅵ」SUNABAギャラリー
2023年 「complex」学内小ギャラリー
「零れ落ちる砂」美術紫水ギャラリー
「京都若手作家展」ちいさいおうち
「ポストKawaii : ハイパーポップ」SUNABAギャラリー
「そこにいるのに」カフェギャラリーきのね
- COMMENT
- この度は六角仏教会賞という素敵な賞を頂くことができ、大変光栄です。今後一層制作に励んで参ります。私の作品が多くの人の癒しになれれば幸いです。
審査員のコメント
授賞式の様子
作品展



































































野口 玲一三菱一号館美術館 上席学芸員
このプロジェクトへの応募は、出品者にとっていささか難しい課題だったのではないかと想像している。個々人の表現世界を追求し掘り下げることと、老人ホームという福祉施設に展示するにふさわしい作品であることにどう折り合いをつけるかが求められるからだ。しかし両立が難しいと感じられた作品はわずかで、多くの作家がうまく着地点を見つけていたと思う。授賞式で各人が自らの作品について語るのを訊いたが、何をしたいのか、何をすべきなのかをそれぞれのやり方できちんと把握して形にしており、日頃の教育と研究の成果であると感心させられた。
作家が社会に対して作品を送り出す窓口にはバリエーションがあり、このようなプロジェクトは特殊なものと思われるが、制作者にとっても鑑賞者にとっても益のあることと思う。作品を常設してじっくりと接することのできる場を提供することになるし、場所あるいは空間と作品との関わりについて考える機会ともなる。そのような経験を作家にさせるという点で教育的な意義もあると思う。展示された作品はたんなる壁の「飾り」であることを越えて交流や賦活の場となるのだ。この事業をぜひ継続していただきたいゆえんである。
正垣 雅子京都市立芸術大学 准教授
表現技法が多彩で、創造の熱意にあふれた作品が多かったことと、コロナ禍を経験して表現に対する想いの再確認や、作品を鑑賞する方への想いを馳せる作家の意識が多くみられたことが印象的でした。入選作品は共用空間に展示され、作家の想いはここに暮す人々に何かを語るでしょう。作品が存在することによって、感性の響き合いが生まれます。暮らしという時間と空間が、豊かに彩られることを祈念します。
安藤 隆一郎京都市立芸術大学 准教授
自身が持つ表現を通して何かを伝えようとする私たちにとって、それが「誰か」のところに届き、その人の日常の一部となることは喜びの一つでもあります。今回、ある出品作家は自身が得意とする表現を用いながらも、その「誰か」を意識し、新しい表現を生み出そうとするところを作品を通して感じました。このように本公募が若手芸術家にとって自身の可能性を押し広げる機会となり、充実したものになっていくことを期待しています。